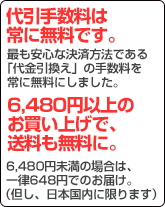Home�@�t�@���N����@�t�@�e�r��v�R�����ꗗ�@�t�@�R����


2006/04/07
�S�Ɛ���(8)
�`��ƌ������Ɓ`
�u�e�͂Ȃ��Ă��q�͈�v�Ƃ������A��i�@�̎Љ�ł��鍡���A���̌��t�͎���ɋ߂��̂ł͂Ȃ����B���܂ꂽ�Ƃ��A2���������זE��60���̍זE�ɑ����āA���̐g�̂͐������邪�A�l�Ƃ��Ă̐��_��N�w�������������ł͂Ȃ��B
�[���e�̈����b�Ƃ��āA�v�����̂���Љ�́A�L�������Ȃ��Ă͐l�͈���Ă����Ȃ��B
���q�����w�I�ɂ́A���ɂ���ė^����ꂽDNA(��`�q)---�����̐v�}�ɂ���āA���̎����甭������q�g�̂��ׂĂ����肳���Ƃ����B
�������ADNA�Ƃ��������̐v�}�̊�{�v�͂ł��Ă��Ă��A���̐���������Ă����ߒ��ɂ����āA�Љ��ƒ�ł̑g�D���m�̉e���̕ω��ŁADNA�̐v�}�ɂ͂Ȃ����߂��厩�R�͍s���̂ł͂Ȃ����B
����́A��`�q�ɂ��ˑR�ψق��N��������A�זE������J��Ԃ��������Ă��邤���ɁA���F�̂̐��ُ̈��`�ُ̈���N����₷���Ȃ�B
�v����ɁADNA(��`�q)�̊�{�v�ʂ�ɂ́A�����������炷��Ƃ͌���Ȃ��Ƃ����̂��������B
�������̐����ɂ͗\���̂ł��Ȃ��ω����N���邵�A�Љ�I�����q(�����A�o�ρA�@���A����A�푈�Ȃ�)�̔�d�͐���ߒ��ɂ����Ă������傫�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�������ݏ���
1920�N10���A�C���h�̃J���J�b�^����12�L���ɂ���S�^�����Ƃ������ŁA�������ݏ������~��������A���E�I�ɑ傫�ȃj���[�X�ƂȂ����B
���̂������ݏ��������A���܂�ĊԂ��Ȃ��������݂Ɉ琬����A�V���O�Ƃ����q�t�v�Ȃ��A���̑��ɓ`���ɍs�����Ƃ��A�l�̉����������ɂ���Ƃ����\������āA�������ꂽ�ƋL�^�ɂ͂���B
�������A��l�̂������ݏ����ŁA�q�t�v�Ȃ͂��̓�l�̏����������������^�c���Ă���ǎ��@�ň�Ă邱�Ƃɂ����̂��B�N��͂������łȂ����A����8��2���Ƃ����B
�A�}���Ɩ��Â���2�̏����͖���Ȃ����S�A�J�}���Ɩ��Â���8�̕��́A9�N�Ԍǎ��@�Ő��������A17�ŕa�C(�A�ŏ�)�Ŏ��S�����Ƃ���B
�V���O�q�t���ڂ����������L�ɂ��ƁA�炩�����͐l�Ԃ����A���̍s�ׂ͑S���������݂������Ƃ����B�����͈Â������̋��ŃE�g�E�g�����Ă��邪�A��͕ǂɌ������܂܂ŁA�قƂ�ǐg��������Ȃ��B�������A��ɂȂ�ƃE���E���ƕ����܂��B�钆�ɂ́A�������݂̂悤�ɉ��ڂ��������Ƃ����B
���s�͓�{�̑��ŗ����ĕ������肷�邱�Ƃ͂ł����A����𗼕G�ł͂�����A����Ɨ������g���đ������肵���Ƃ���B
�q�t�v�Ȃ̂�������������ɂ�������炸�A���������ɂȂ��Ȃ������B�ق��̎q�ǂ������Ɋ���Ă���Ǝ����ނ������ɂ��āA����Ȑ������B�������b�����ł��Ȃ����A���t�̗������s�\�ł��������A3�N�����ė����ŗ����ĕ����悤�ɂȂ������A�}���Ƃ��͎l�{���ő������Ƃ����B
���̂������݂̏K���͎��ʂ܂ő������Ƃ���B
����ł��A�V���O�q�t�v�Ȃ̈琬�w�͂ɂ��A����g���ĐH�ׂ邱�Ƃ��ł��A��т�߂��݂̐S�̕\�����ł��A4�`5�����炢�̌��t���g���܂łɂȂ����Ƃ����B
���̂������ݏ��������łȂ��A�����������l�Ɩ��J�̒n�ɏZ�ސl�Ƃł́A�]�̓����ɑ傫�ȈႢ������B���R���͂����܂ł��Ȃ��A�Љ�I���̏d�v�����傫���e�����Ă���B
�������̔]�����A���܂ꂽ����̐Ԃ����͖�400g�ƁA�g�̂̂ǂ̕��������傫���A�܂����̔��瑬�x���A����6�����Ő��܂ꂽ���̏d���̓�{�ɂȂ�A7�A8�ő�l�̏d����90%�ɒB���A���̌�́A�������Ɣ]�͑傫���Ȃ��Ă����B������20�ΑO��Ŋ����A50�`60���߂���ƁA�]�͂��₩�Ɍy���Ȃ�ƁA���Ƃ͏q�ׂĂ���B
�]�̔��B�ɂ���
���̘A�ڑ�3��ŏڂ����q�ׂ����A�_�o�זE�ƁA��������L�т�_�o�ˋN(�����Ȃ�)����̒P�ʂƂ��ăj���[�����Ƃ������A���`�B�̂��߂ɁA���̃j���[�������m�����ݍ����āA�]�̋@�\�����B����B�_�o�זE�͐��܂ꂽ�Ƃ��A���̐��͊������Ă���̂ŁA�Đ��͂��Ȃ��Ƃ����Ă���B�������A�ŋ߂̌����ŁA�Đ������蓾��Ƃ������Ƃ�������悤�ɂȂ��Ă����B
���̂��Ƃɂ��ẮA��̏͂ŏq�ׂ����B
�_�o�זE(�j���[����)���m�����̔z���𖧂ɂ��邱�Ƃ��A�]�̔��B���Ƃ�����B
�]���Đ��܂ꂽ����̐Ԃ����̖��n�Ȕ]�́A���i�Ƃ��Ă̐_�o�זE�͏o�����Ă��邪�A�܂��܂����̔z�����Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B
���܂�Ă���3�܂ł��A�͕킷�鎞���Ƃ����A4����10���炢�܂ł��A��������
�����鎞��(���䂪�ł���)�Ƃ����B
���̐_�o�זE(�j���[����)�̔z���́A3�Ύ��܂łƁA4����10���炢�܂łƂł́A���ꂼ�������]�̕��ʂōs���Ă���Ƃ����B���̑��x���A�O�ɏq�ׂ��]�̏d���̂悤�ɁA3�Ύ��܂ł�4����7�Ύ��܂ł́A���̃X�s�[�h�͑傫�����A10����ƁA���̔z���͂������Ɛi�߂���Ƃ����B
�]�̐��Ƃ̎������F���́A�u�l�Ԃł��邱�Ɓv�Ƃ�������(��g�V��)�̂Ȃ��Ŏ��̂悤�Ȃ��Ƃ��q�ׂĂ���B
�u����̖ړI�͐l�Ԍ`���ł��邩��A�_�o�זE��l�ԂƂ��Ă̐��_�������A�l�ԂƂ��Ă�
�s�����ł���悤��---�]���āA�_�o�זE�̔z���̉ߒ��ł���]�̔��B�ɑ������琬���Ȃ����Ƃ���ɁA�ۈ�A����̉Ȋw���A�ߑ㐫������͂����v
�Ƃ����u�l�Ԃ͋��炳��Ȃ���Ȃ�Ȃ������ł���v�Əq�ׂĂ���B
�����A3����p����w�ق��������Ƃ��A�c���ɑ���Z�~�i�[�������A�^�̐l�Ԍ`���Ƃ��Ă̋���͂ǂ��ɂ��邩�Ƃ����ƁA���̓����͓���B�������Ƃ������B
�玙�̎��R��
����}���A���A�c���L���X�g�����ɕ����Ă��邻�̎p�ɁA���̌��_���݂邱�Ƃ��ł���B
���Ȃ����Đl�͈炽�Ȃ�---���̂��Ƃ���������Ƌ������Ă����B�����Ď������l�Ԃ̐����̖{�������A�����Ɍ��邱�Ƃ��ł���B
�a���ƂƂ��ɕ���ɂ���āA�q�ǂ��͈���Ă����B����͂��炵���B�h�{�̃o�����X���悭�Ƃ�Ă���A�^���p�N���͏������₷���A�G�l���M�[���Ƃ��đ�ȓ����́A���̓����̓���葽���܂܂�Ă���̂��B
���،㐔���Ԃŕ��傷�邪�A�������̖Ɖu�O���u�����́A�A�����M�[�Ǐ�⒰���Ȃǂɑ����R�͂����邱�ƂɂȂ�B
���̚M���̊Ԃł��A�͂��߂͔���������ɔZ���Ȃ�A�����Ƃ��Ď��b�������ĐH�~�߂���Ƃ����B���̖��E�����̕ω���Ԃ����͊o����B
�����ōł��厖�Ȏ��R�̎d�g�����A����͓�����z���邱�ƂŁA��Ǝq�����̈�����[�߂�ƂƂ��ɁA������z���s�ׂ́A���̐_�o���˂����e�̔]�����̂��h�����A�v�����N�`���ƃI�L�V�g�V���Ƃ�����̃z�������傷�邱�Ƃ��B���Ȃ킿�A�v�����N�`���͕��������厖�ȃz�������ł���A�܂��₳����(�ꐫ��)���������������z�������ł���B�����ăI�L�V�g�V���́A���B�̓��ǂ��h�����āA��������[���番�傷�铭���������Ă���B���̃I�L�V�g�V���́A�����ɂ̂��Ďq�{�ɉ^��A�Y��̎q�{���k(����ɂȂ�)�����铭��������B
���āA�S�̔���ɂ́A�������̖��_������B
���̑��̂��Ƃ����A2�l�̒j�̎q������B
�Z�͏��w���A���3�Ύ��B���̒�ɖ�肪�N�������B����́A��e���}�p�ŁA�����������Ȃ��A���Ԃ̈ꎞ�I�ɗc����a�����Ă���鏊�ɂ��肢�����̂����A��e���}���ɂ��鐔���ԁA�������ђʂ��������Ƃ����B�a�������l�͒j���ŁA�ӂƕs���ɂȂ������A�ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ������B���̌�������a�������A�u�}�}�ɉ��������I�}�}�ɉ��������I�v�Ƃ�͂苃�����Ƃ����B
���̂����������Ԃ̂��ƂŁA���͕�e�ɂ����݂�����A�t�ɔ��R������A��e��ǂ��s�ׂɈُ킳���łĂ��܂����̂��B
���݁A5�����A�Ȃ�Ƃ����������݂���悤�ɂȂ������A���Ȏ咣���ُ�ɋ������Ƃ�����B����3�̎��A���̐�����̂��Ƃ��A���|�S�ƂȂ��āA�]�ɂ����܂ꂽ�̂�������Ȃ��B
���܂ꂽ�Ă̐Ԃ����́A��e�Ƃ����e�Ƃ������ӎ��́A�����܂ł��Ȃ������Ă��Ȃ����A��������ɂ�āA���������ɘA���I�ɂ�������Ă����l���A��(�}�})�A���邢�͕�(�p�p)�Ƃ����悤�Ɉӎ��������B
�������āA�Ԃ����̐S�͈��肵�Ă����̂����A�e�̔������s���肾�ƁA�S�͓��h���āA���ꂩ�����䂪�ł��ɂ����Ȃ�Ɛ��Ƃ͏q�ׂĂ���B
���̂悤�Ȃ��Ƃ���A�Ԃ����̈��肵���S���ł���܂ł́A���낢��Ȑl�Ɩ������Ɋւ��Ȃ��ŁA�e�Ȃ�e�A���邢�͎傽��ۈ�҂��ւ���Ă���ق����]�܂����Ƃ������Ƃ��B
�ŋ߂́A���ꂳ��������Ă���A���܂�Ă���(�����͐���8��������)���l�ɗa����P�[�X�������Ă���B���̑��l�����������l��������A�e�Ƃ��܂芴���̈��Ȃ��l���Ƃ����̂����A�e�Ƃ܂������ԓx�̈Ⴄ�l�ł�������A���邢�́A��l�A�O�l�Ƃ����ƕς����肷��ƁA�Ԃ�����c���̎���̊�{�I�ȑԓx���ł܂�Ȃ��Ƃ����B
�玙�̐��Ƃ́A�܂���{�I�Ȑl�ԊW�̃p�^�[�����ł��Ă��Ȃ��Ƃ��A�ۈ�@�ցA���Ȃ킿�A�q�ǂ���a����ق����A���̓_���\���ɒ��ӂ��Ȃ��ƁA�ނ������̋����W�Ɋ������܂�āA�����q�͎ア�q���A���������ނ���悤�ȏK���A������H���g�ɂ��Ă��܂��Ƃ����B�t�Ɏア�q�́A�������o���Ȃ����ƂŐg�����悤�ɂȂ�A���I�Ɋ����\���Ȃ��Ȃ�Ɛ��Ƃ͎w�E���Ă���B
�e�ɂƂ��Ă͂����̂����A�q�ǂ��ɂƂ��Ă̓}�C�i�X�ɂȂ�ʂ��傫�����Ƃ�S���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����낤�B�ۈ狳��̏d�v���������ɂ͂���B
�����O�����҂̗ѓ��`���́A�����w�S�̂����݂�T��B�����O�S���w����U�v(PHP�V��)�̂Ȃ��Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
(�����OCarl Gustar Jung---�X�C�X�̐S���w�ҁA���_��w��(1875--1961)�ŏ��t���C�g�̐��_���͂ɋ��A���̌�Ǝ��̕��͓I�S���w���m��)
�u�Ԃ���班�N�����Ɛ������A�Ƒ���Љ�̉e���̒��ŁA����̉��l�̌n�Ƃ����̂��ꉞ�ł��Ă���B�Ƃ��낪�A���̉��l�̌n�����m�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ́A��̑I������悤�ɂȂ�Ƃ������Ƃ��B
�܂�A�P�����������߂āA�悢�ق���I�тƂ�A�����ق��͎̂Ă邱�ƂɂȂ�B���䂪�͂����肵�Ă������قǁA�����̂Ǝ̂Ă���̂��͂����肵�Ă���B
�܂����Ƃ������̂��A�S�̒��ɐ��܂�Ă���B���̂��Ƃ͎��䂪�͂�����`������Ă��Ă���Ƃ������Ƃ������Ă���B
�S�̒��Ɉ����C���[�W���o�Ă��āA�����A�U�������肷��Ƃ������Ƃ͔��ɑ�ŁA����͎��䂪���܂���邱�Ƃ̏؋��ł���B�v
�Ƃ���A���̐S�̌��ۂ��\���Ɏ������Љ�͗������邱�Ƃ��厖���Ƃ�����B
�܂��e�̎���---��d�l�i�Ƃ������ڂŎ��̂悤�ɂׂ̂Ă���B
�u���܂�ɂ��ے肪�����ƁA�ے肳��Ă�����̂��������ď���Ȃ��Ƃ����悤�ɂȂ��āA�ʐl�̂悤�ɂȂ�B�����Ă��ꂪ�����������Ă��܂��Ɠ�d�l�i�ɂȂ�B��d�l�i�Ƃ����̂́A�e���Ƃ��ǂ����̐l�̐l�i���������Ă��܂����ƂɂȂ�B���̂��Ƃ�---���̐l�Ԃ̐l�i�ōs������悤�ɂȂ�v
���ۂɎ��������̎q�ǂ����݂Ă��邪�A��e�╃�e����A��Ɂu���O�͓��������A���O�͑ʖڂ��v�ƌ���ꑱ���Ă���ƁA�����܂ł��Ȃ��e�Ƃ̊W�͂��܂��������A���w�⍂�Z�𒆑ނ��āA�Əo��������A�ƍ߂̓��ɑ����Ă��܂��������B�܂��A�����܂ł����Ȃ��Ă��A���̎q�ǂ��́A���ɂ���Đe�ɑ��鑞���݂�S�̒��Ɏ����A���ꂪ���U�ɂ킽�邾���łȂ��A���̐e�����E���Ă��A���̑����݂͏����Ȃ��B����ȗ�𑽂��݂Ă���B
�Ƃɂ����A�e���\���Ɉ���𒍂��ł��Ȃ��ƁA�q�ǂ��̖{���̐S�̈琬���j�Q�����B
�e�ɉR��������A�����������������A�s�lj����邱�Ƃ�����̂��B
�܂��u�́v�������
�O�ɂ��Љ�����A�����Ȉ�Łu�q�ǂ��̔]�͔��ɂ���v�̒����R���n���́A���A�́A�S�̎O��---�܂��̂������ׂ����Ƃ����B
��������(�c������)���A���ׂĔے肵�Ȃ����A���̑����͐e�̂��߂ł����āA���̎q�ǂ��̂��߂ł͂Ȃ����Ƃ������̂ł͂Ȃ����B
�R���n���́A���̒����̂Ȃ��ł����q�ׂĂ���B
�u7����12���炢�܂ł̎����́w��̓I������x�Ƃ��A�ςݖȂǖڂ̑O�̋�̓I�Ȏ����̑���Ȃ��ɂ͌v�Z�ȂǁA���ۓI�ȑ���͂��܂��ł��Ȃ��B
������12�Έȍ~�́w�`���I������x�ɂȂ�ƁA�ڂ̑O�̎������Ȃ��Ă��A���ۓI�Ȍ��t�␔���̑��삪�ł���悤�ɂȂ�v�Ƃ����B���̏����̂Ȃ��ŁA�����C�ɂȂ������ƁA�뜜�������Ƃ́A�ꌩ�A�q�ǂ��͔M�S�ɕ����Ă���悤�ł��A�����I�Ȉӎv�ł���Ă���킯�ł͂Ȃ��B����ȃP�[�X�ł́A��������ߒ��ŁA�ړI���������j�]���A�u���a�v��u�R�����nj�Q�v�ɂȂ�������Ƃ������Ƃ��B
�l���̖ړI������������߂ɂ́A�e�̈���邵���₫�т�������̒��ł��A�������g�̎�̐��������āA���Ƃ��ǂ�ȏ����Ȕ�����������Ƃ��Ă��A���̂Ƃ��ɂ͊�т������āA�Ƃ߂Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�����ӂ�Ǝv�t����N���ɂȂ��āA���䂪���������Ƃ��S�̕a�ǂ��邱�Ƃ�����Ƃ������Ƃ��B �e�Ǝq�̏�ɂ���Θb�́A���݂��̐S�̐����ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�}���`�^�C�v �~�l���� |
�Z�b�g�^�C�v
�b��̉h�{�f |
�r�^�~�� |

�T�v�������g�ʔ̃z�[���@�@�T�v�������g�ꗗ�@�@���N��������
�����E�|�C���g�ē��@�@�悭���鎿��E���⍇���@�@��ЊT�v�@�@
c 2005 A'prime, All Rights Reserved. Tel: 043-279-1708 Fax: 043-278-7004 Privacy