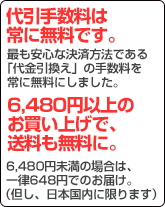2005/04/12
2.医師と死
〜ガンに罹った医師たち〜
死と生と向き合う
強靱な精神力など、私は持てないだろう。弱い人間である。
ただ私のような病者は、生のなかに死をおかねばならない。死を先き取りすることによって、生はさらに新鮮でかけがえのないものになるのではないか。----そこには生命の自然性や心の純粋性が持てるからだ。
私は死と闘うという大それたことはしまい。日々を大事にして、内科的な投薬治療でいくしかない。そう覚悟を決めた。
そこで学会でいつも一緒になる親友の専門医にかかることとしよう。そう方向を決めた。
私の既往歴を知っている妻も息子夫婦も「大事にしてください」と一言やさしい声をかけてくれた。家族に対する愛着の念が、激しい勢いで心から込み上げてきた。
それにしても死を問うことによって、多くの問題点が脳裡に浮かび、やがて具体的な事柄として迫まってきた。その第一が、多くの教えを受けた著名な医師たちの死だった。
医師たちの死
医師は、がんの臨床医だった。
C型肝炎から肝がんに移行した後の死だった。
肝炎は、かなり昔から慢性的にあったらしい。病状そのものを誰にも話さず、長い年限、医師として、患者として苦悩してきたことだろう。
時々肝機能検査の数値が異常に悪化すると、自分が勤務している病院に入院したが、治療の合間をみて、臨床診療の指導を続けていた。
時々お会いしたが、強気で明るかった。そしてやがて肝がんが発症。外科治療もせず、抗がん剤を使っていた。詳しい病状は誰も知らない。
入退院を繰り返しながらも、臨床医として患者の治療にあたった。お会いするたびに、A医師のからだが小さくなっていく。お見舞の言葉などかけられない。なんとも言えない根源的な強い精気を感じたからだ。
しかし、部下である医長にすべてを委ねて死を迎えた。
B医師は、明るく積極的な、いわゆる行動派で、東京のF大学の助教授から京都の大学の教授になった。眼科の専門医である。移殖全般の政府専門委員もしていた。
ある日、仕事の確認のため電話をかけた。相も変らない元気な明るい声で、来週は必ず約束の日時に上京するという。話をしているうちに、この電話が、病院のベッドからだったことがわかった。血尿から腎臓がんと診断され、腫瘍のある腎臓を摘出したという。これしかないから、そう処置をしただけさ----笑っていた。
定年後は、ある市の市立病院長として第二の人生を張り切って始めた。
ところがある日、突然のように、「私は、脳神経内科領域の疾患にかかり、どうにもならない難治性の脳疾患であり、今日ただ今をもって、すべての職を辞しました」
という印刷された挨拶文が郵送されてきた。彼は完全に社会から離れ、家にこもってしまったのである。
亡くなった後で、奥さんから聞いて知ったのだが、まだ病状がそれほど進行していない時、毎日のように一人で小さな旅をしたという。その旅は自分が眠るべき寺院・墓所をさがしての旅だったという。しかし結果的には、家族のいる自宅から数十分の寺院に決めたと奥さんは、苦笑しながら言った。
家庭での療養生活は、病気の進行に伴い苦しく辛いものになり、歩行困難はいうに及ばず、寝返りもできなくなり、肺炎を併発、救急車で大学病院に搬送----。しかし、この搬送する車の中でも、酸素吸入を自らの手で外し、病院での集中治療も強く拒否した。壮烈な死だった。
C医師は、高血圧症や心臓病など循環器の専門医であった。国立大学教授から定年後は私立大学の教授に移った。
病気は大腸がん、外科治療をしたが、その効果はなく、末期になった。
私は週に一度くらいお見舞に行ったが、「君、調子がいいでしょう。
顔色がいい」と、私の顔をみて、視診をする。24時間ベッドにいても、常に医師だった。
病状がさらに進み、麻薬による鎮痛治療からか、現実と非現実の世界が混在するようになったとき、手帳を出させ、長い付き合いの何人かの患者一人ひとりに枕辺から電話をかけて、最後のお別れをした。こうして四〜五日後には、昏睡状態となり、還らぬ人となった。
ここでいいたいことは、ベテランの医師だからこそ、自分の生命の限界をはっきりと分かっていたということだ。
今日、終末医療では、トラブルが多い。患者や家族に、生命の限界をはっきり示す----そんな医療環境を専門的に行う科が必要なのではないかということだ。
人は生れてくるとき産科という専門科がある。死ぬときは、この産科に対して死科なる専門科が、患者や家族も参画して存在しても当然なのではないか。
医療は検査、診断、治療、延命という組み合わせで行われる。ここまでは一般の疾患でも不治の病であっても同じなのだが、診断の結果、残念ながら不治の病であった場合、患者本人の主体性がどこにあるのか、疑問を抱くことがある。医療そのもののなかに、死を忌むという、死を嫌ってさける面があり、そのことが表面化する傾向がよくある。
本来、死に対する医療というものが暖昧で、人がどのように死に至るか、その過程について詳しいことも、大事な広い意味での治療指針が必要だといえる。
この指針がしっかりと医療のなかに確立していないため、患者も家族も迷い、医師も迷い、あたかも助かるかのごとき特殊なイカサマ治療が登場してくる。死に至る過程が複雑化している面も少くない。
死は、患者にとっても、家族にとっても、医師にとっても、すべてを超越する最も人間的な愛の世界ではないのか。
医療人はいうに及ばず、私たちは死を現実の間近な重大問題として、日頃から学び合うことが必要だ。
この学びのなかから、病を認識し、死を悟って、限られた生命力のなかに人生があり、生命の尊さがあるということを、互いに学び合う医療を創っていくことになるのではないか。
それにしても、現代は残酷な死が多い。
残酷な死
一個の受精卵が60兆個の細胞に増え、人間という小さな宇宙を形成する。限りある貴重な生命である。
しかし、この生命を瞬時にして奪う殺し合いほど残酷なものはない。
原爆をはじめ多くの近代兵器は、生命の根源であるDNAの塩基配列を狂わし、悲惨な疾患を後世に発症させている。
まだ何も知らない純粋そのものの小さな子供たちの殺人には、強い怒りを感じる。
イスラエルとパレスチナの戦い、イラクの戦争にしても、正義の名における殺戮などあるはずがない。
残酷な死はそのまま残酷な心を生み、地獄に似た生へと連鎖し、人が人を生むことができない生命体となって滅びてしまうのではないか。
マルチタイプ ミネラル |
セットタイプ 話題の栄養素 |
ビタミン |

サプリメント通販ホーム サプリメント一覧 健康情報を見る
送料・ポイント案内 よくある質問・お問合せ 会社概要
c 2005 A'prime, All Rights Reserved. Tel: 043-279-1708 Fax: 043-278-7004 Privacy